“文理融合”で拓く、生体イメージング技術の新しい価値観。
「理工学的な“ 画像技術の質” の追及」×「脳科学・心理学から考える“医療の質” の追及」
人類は、今日の高度な医療を形成する診断・治療・予防に関する各技術やそれに関連する創薬・基礎医学・生命科学の分野における多くの知識を、生体を対象とした「視覚的な観察と計測」を通じて獲得してきました。
これらの技術や知見の獲得は各種イメージング機器を始めとした生体計測技術に対する不断の開発努力とその技術の進歩によって支えられてきました。このような技術的進化への貢献のため、本研究室ではX線やγ線などの放射線を活用した量子イメージング技術(陽電子断層撮影法(PET)の核医学技術やX線CTを始めとした放射線医学技術)の開発を進めています。その研究アプローチの特徴が、異なる多分野からの視点:画像工学・半導体工学や物理学などの「理工学的な視点」と、心理学・脳科学などの「人文科学的な要素を含んだ視点」から技術構築を目指す点です。このようなユニークな研究アプローチを通じて、これまでの生体医工学には無かった新しい価値観を提案することを目指しています。
本研究室が挑戦する1つ目の技術的価値が、理工学的な観点での限界を上回る画像性能の達成です。各種の医療画像モダリティ(=医療機器の種類)の性能には物理的上限が存在します。そして、例えば「超解像度イメージ」と呼ばれる画像技術などはそのような物理的な制約によって定まった上限を超える解像度を達成した画像のことを指します。そのような新しい画像技術の構築を目指して本研究室でも研究開発を行っています。
また、本研究室が描く新しいもう1つの価値観が、「医師等の診療パフォーマンスの最大化と、医療事故・過誤の回避に寄与する医工学技術」です。理工学的面での技術向上は確かに医療の高度化に不可欠ですが、最終的な技術の価値はそれらを活用した医療従事者が患者に提供しうる医療の質によって決まります。本研究室では脳科学や心理学などの理工学以外の分野の方法論や知見を応用し、医療従事者が開発された技術に対して惹起する思考や心理を生体計測情報に基づいて予測する文理融合型の技術評価・最適化の手法の確立に向けた研究も行っています。
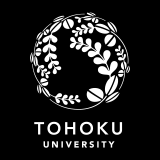
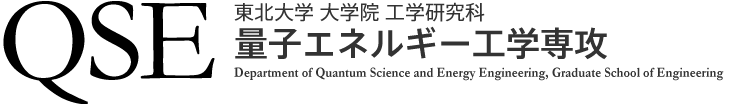

 准教授
准教授